BUMP OF CHIKENヒストリーブック
2004年発売「アルエ」の応募企画に当選した限定3000冊のヒストリーブックの内容。
合わせて読みたい
目次
4ピース完成“ガラスのブルース”-高校時代-
| 藤原 | 「高校受験終わってまた集まった時って、まずビートルズをいっぱいカヴァーしたよね。文化祭で”ツイスト・アンド・シャウト”とか”スタンド・バイ・ミー”とか、いわゆるシンプルなロックンロールのナンバーをやって、これがバンドで合わせるってことの基本なんだって肌で感じて、面白いと思って。だから自然と そういう方向に流れたの。で、俺ら、ライブのやり方がわかんなかったんだよな。ライブハウスでやるなんて300万とかそういう単位の金が必要なんじゃねーかなって思ってたし(笑)」 |
| 直井 | 「それで、ライブやるにはどうしたらいいんだろうって言ってたら、ヒデちゃんが『こういうのがあんだよ』って、なんか『全国高校生音楽祭』のね、チラシを持ってきてくれたの」 |
| 藤原 | 「そうそう。『青年の主張』の音楽、バンド・ヴァージョンみたいな」 |
| 直井 | 「ちょうどその頃、藤原が”デザート・カントリー”っていう素晴らしい曲を書いて」 |
| 藤原 | 「とりあえずオリジナル曲を書いてみたいなーと思って、中3から高1の春休みに書いたんだよ。詞はみんなで書いたんだよね」 |
| 直井 | 「俺の部屋で」 |
| 藤原 | 「英語の辞書と照らし合わせながら。たぶんめちゃくちゃだと思うよ。だって名前がバンプ・オブ・チキンだもんね(笑)」 |
| 直井 | 「だからその大会に出るって時に、エントリーするにはバンド名が必要だってなって、じゃあ考えようかっつって」 |
| 升 | 「そしたら藤原が、すげーブルージーだから『トラクター』がいいって(笑)」 |
| 直井 | 「俺は『カントリー・コンベアー』みたいなこと言ってた」 |
| 藤原 | 「俺は絶対『トラクター』がいいって笑。『ダセェよ』『じゃあブルー・トラクターは?』『全然ダセェよ』とか言われて。そいでヒデちゃんがが、3つのなんかがいいっていったの。『~・~・~』みたいな」 |
| 直井 | 「それでじゃあ俺らを表そうってことになって。俺らって、どっちかっつーと……」 |
| 藤原 | 「どうしようもないじゃんって」 |
| 直井 | 「だから弱者とか弱虫みたいな……」 |
| 藤原 | 「腰抜けね」 |
| 直井 | 「それで『チキン』。で、そいつらがガーンってやる感じっつーのはどう言うの?って」 |
| 藤原 | 「それで『衝突』とか『激突』とかそういうの調べたら、『バンプ』ってあって」 |
| 直井 | 「で、『~の』ってのが『オブ』だから、『弱虫の衝突』とか『突撃』って意味でバンプ・オブ・チキンにしたんだよね。ところが……」 |
| 藤原 | 「ところが、英語として意味を成してなかったんだよな(笑)」 |
| 増川 | 「だから一時期バンド名ちょっと変わった時期あったよね」 |
| 直井 | 「バンプ・”オフ”・チキンにしたんだよ」 |
| 藤原 | 「『腰抜けを踏み潰す』(笑)」 |
| 直井 | 「それは1回で終わったんだけど(笑)」 |
| 藤原 | 「バンプ・オブ・チキンって名乗った時点で、その名前自体がとっても嬉しくて、意味なんかどうでも良かったんだよね」 |
| 増川 | 「嬉しかったな。ノートに書いたりしてたもん」 |
| 直井 | 「早速ベースに刻んだりして。で、その大会も、テープを送ったら予選通過して」 |
| 藤原 | 「つかね、その大会ってなんだかよくわかんなかったよね。純粋に『音楽』ってことではなくて、まあ要は『主張』だったの」 |
| 直井 | 「でも、俺ら英語の歌詞だったじゃん」 |
| 藤原 | 「(笑)俺ら……なんで”デザート・カントリー”になったんだっけ?」 |
| 増川 | 「だから、ボン・ジョヴィの……」 |
| 直井 | 「ブルージー感だよね」 |
| 藤・升 | 「ブルージー感!(笑)」 |
| 増川 | 「水牛の頭を家に飾りたい気持ちが”デザート・カントリー”になったんだよ(笑)」 |
| 藤原 | 「ハーレーダビットソンに跨って、グランドキャニオンを疾走するっていう」 |
| 直井 | 「そん時俺らの中で流行ってたんだよね。もうヴィジュアル系とかなくなってて、藤くんが持ってきたハード・ロックとか、そういうのばっか聴いてたよね」 |
| 藤原 | 「高1の初めハマったのがハード・ロックだったからさ」 |
高校時代~DANNY~
| 直井 | 「で、大会出て。リハーサルってもんが何かわかってなかったから、リハーサルで全然違う曲やってんの。”スタンド・バイ・ミー”やってんだよね(笑)」 |
| 藤原 | 「みんな、すっげー黙ってて。こりゃ俺ら、いい演奏したんだな、度肝抜いてやったよって。まあなんてことはない、『なんでこいつらエントリー曲と違う曲やってんだ』って疑問の目だったんだけど(笑)。でやっぱりダメだったんだけど、スタッフのひとに俺らの評判聞いたら、『人気投票結構高かったよ、2番目くらいに高かったよ』って言われて。『じゃあ俺ら千葉で2位なんじゃん、すごくない?』って。だからすごい前向き思考(笑)。みんなで軽井沢にバンド合宿とかに行ったりして。でも演奏してた時間なんてほんのわずか。あと何やってたかっていうと、ほんと飢えと苦しみ(笑)。そういう時期を過ぎてって。その時もうひとりメンバーいたんだけど、そいつは結構とっぽい奴で。合宿行っても、なんかいい出会いがあったらいいなーみたいな」 |
| 増川 | 「逆に今時の奴だったんじゃない?」 |
| 直井 | 「一番普通な奴だった。モテたし」 |
| 藤原 | 「俺らは女の子に声かけるなんて怖くて出来ないよって、妄想で終わるタイプ。そいつは実行するタイプ。で、やっぱソリが合わなくなって。俺と一番仲良かったから、俺は橋渡し的な感じにしてたんだけど、やっぱ俺とふたりになっちゃうことが多くて」 |
| 直井 | 「俺、嫉妬してたもん。そっちに行ってる時の藤くんがあんま好きじゃなかった」 |
| 升・増 | 「(笑)」 |
| 藤原 | 「(笑)『もっとあいつと喋ってやってくんねえ?』みたいなこと言ったりしたよね。で、増川は結構、柔軟にやったりしたんだけど」 |
| 直井 | 「特に俺だ」 |
| 藤原 | 「チャマは練習場所提供してて、親に対する引け目もあるわけで。でもそいつはモテたいだけでやってる。全然別にいいんだけどさ、それもさ。俺らも似たような動機だし。初めから『僕は音楽をやるために生まれてきたんだ』みたいな、そんなんじゃなかったからさ。でもそいつ、いつも練習遅れて来て、遅れてきた後も寝たりとか。たまに音出したかと思えば、すごいチューニング狂ったまま弾いてたり。……まあ今思うと、温度が合わなかっただけなんだよね。で、家出したんだよ、そいつが。その理由が、バンドやりたいって親に言っても認めてくんなくって、『だから俺、ストライキで家出たんだよ』っつう。でもそういうこと言ってても、ギター買うって貯めてたお金で服を買っちゃったりしてたから(笑)。そういうとこで俺らと温度違うなってとこがあった。全然わかるんだけどさ(笑)。で、家出して、迷惑なことに俺ん家のすぐ近くの公園に来ちゃって。俺、結構駆り出されたりして(笑)。毛布とか持ってったり」 |
| 増川 | 「俺はなんか缶詰持ってった」 |
| 藤原 | 「でも可哀想に健康管理がまずかったせいか、湿疹が出来ちゃったりして(笑)。その横でね、ぼけーっと話聞きながら、『だってお前ギター買ってねーじゃん』とか思いながら、”ダニー”を書いたんだ」 |
| 直井 | 「そうなんだよね」 |
| 藤原 | 「そうやって”ダニー”が出来て。あ、この曲いーじゃんって思って。”デザート・カントリー”はやれりゃいいって感じで作った曲だったんだけど、”ダニー”は結構純粋……純粋っつたら嫌だけど、邪念がない感じで。『音楽って楽しいな』とか『こういう感じの曲ってカッコいいな』とか、そういう気持ちだけで書いたのはあれが初めてだった」 |
| 直井 | 「それが、初めて藤原だけで作った曲。だから作詞作曲・藤原基央の始まり」 |
| 藤原 | 「あ、でも、やっぱ作詞ん時は知恵借りた記憶がある(笑)」 |
| 直井 | 「でも知識的なことだけだったよ。ヒデちゃんが『ここの文法はおかしいよ』とか。だからもう詞に関しては、誰も口出してない」 |
| 藤原 | 「あの詞はさ、雑誌かなんかで読んだのかな、わかんないけど、『結構あったことをそのまんま書くひとって多いんだな』って思って。で、俺犬飼ってたことがあったから、その犬の歌書いてみようってとこから始まったの。内容はさ、朝起きて庭に出てみたら犬がいねえと。どこ行ったんかなって探しに行ったら、隣の家でそこの犬とめちゃめちゃ闘ってたっていう(笑)。で、『頑張れ頑張れ』ってひたすら応援するっていう曲だった」 |
| 直井 | 「俺、初めてメッセージがあるっていう気持ちを覚えた。そういう応援してる気持ちとかさ、初めてメッセージをやってるっていう。だからなんか気持ちいいの、演奏してて」 |
| 藤原 | 「まだ英語なんだけどね。でもみんなで合わせた時、すごい喜びがあったよね」 |
| 直井 | 「あったあった」 |
高校時代~4人で大会出場~
| 藤原 | 「で、そんなこんなの時、高1の終わりぐらいに、雑誌に載ってた某大会に出てみようってことになって。で、エントリーするんでメンバー名を書くって時に、もうひとりのギタリストをどうしようってなったんだよね。それで協議の結果、『4人で出てみっか』ってことに」 |
| 直井 | 「内緒でね(笑)」 |
| 藤原 | 「どうせ優勝とかでもないだろうしって感じで。でも出てみたら、結構な結果を出しちゃったの。地区大会勝ち上がって、次に千葉ブロック。それは千葉パルコでやって」 |
| 直井 | 「すごい広かった。俺駆けずり回ったよね」 |
| 藤原 | 「そうそう。変なカッコしてたよ。頭にスキーのゴーグルつけてた(笑)。で、それも勝っちゃったの。そいで、ボチボチ友達もそういうのを観に来てくれるようになって。それで最後、日本青年館に立ったんだよな」 |
| 升 | 「それが関東大会」 |
| 藤原 | 「その先には行けなかったんだけど。でも、さすがに地元にそういう噂は広まってて。で、帰ってきたらやっぱりそいつも知ってて。悪りぃことしたなって、すごい思ったんだけど、やっぱ残念ながら、友情の物語よりも結果がすべてだった部分があったりして」 |
| 直井 | 「やっぱ4人の方が良かったんだよね」 |
| 藤原 | 「すごいシェイプされてたんだ、音が。だから音が答えを語ってたんだよ」 |
| 直井 | 「なんかね、5人だと合わせてる感じしなかったんだけど、4人だと合わせてる感じになったんだよ。で、その大会の時に、初めて某音楽会社の人から声がかかって。それで4人で東京に行って。したら言われたことは……」 |
| 藤原 | 「『なんで英語で書くの』って聞かれたんだよね。で、その時ちょっと洒落こいちゃってね、デケェこと言ってやろうと思って……」 |
| 直井 | 「『世界に通用する』みてーな」 |
| 藤原 | 「そういうこと言っちゃって。『バッカヤロー、お前まず日本で通用するような詞書けよ』って言われて。その通りだと思った。ムカついたけど言い返す言葉がなくて。でも英語で書いてたよな、しばらく」 |
高校時代~高校中退~
| 藤原 | 「俺、その大会の時はもうとっくに高校辞めてて。辞めたの高1の夏だったから。・・・・空っぽだったね。俺さ、学校行かなくなっちゃったんだよ、もう面倒くさくて。だって、昨日観たテレビでこんだけおもしろいことがあったんだよとかさ、こないだ街で見かけて傑作でさ、みたいなこと話せば、バンプ・オブ・チキンはどっかんどっかん笑ったじゃん、みんな。だから相当なもんを共有できたわけさ。で、高校でも同じ様なことをしたいわけじゃん。でも話してるときも、みんな単語帳を捲ってるわけさ。だって入学して、突然『志望校はどこですか』って聞かれんだよ?意味わかんねえと思ってさ。 だから学校行っても寝てて。まあ仲良い友達もいたけど。 バンドやってるひともいたから、助っ人みたいな感じで一緒にバンドやったりとかしたけど。でもそんな体たらくで。 みんなさ、歌ったりすれば『お前すげーな』って言ってくれるさ。でもその程度じゃん。大したもんじゃねえと思ってたし。したら出席日数足りなくなって留年だってなって、 辞めるしかねえなと思って。でも辞めてどうするんだって自問自答—- 自分で聞く部分もあったし、親もそう聞くし。『いやバンドやるよ』とか言うんだけど、ほんとにか? ほんとにやんのか?って思ってたりもしたし。 で、辞めて……うん。あん時死んでたね(笑)。ていうか、片足突っ込んでたね。俺が学校辞めて、メンバーみんな、ウチに来てたじゃん、代わる代わる」 |
| 直井 | 「ローテーションでな」 |
| 藤原 | 「ローテーションで。時には一緒に。『お前バイト探したのか』『いや別に探してねえよ』『探せよ』『いいよ面倒くせえ』、そういう感じだった。ほっといてくれよみたいな。ギターとか弾いたりしてた。ひとと会ったりもしてたけど、なんか……『よくわかんねえ、よくわかんねえ』とか思ったりしてた」 |
| 直井 | 「俺らは俺らですごかったもん。まだ17~18とかだし、普通のベーシックな生き方から外れちゃったひとって初めてだったから。まあその前に、俺はもうちょっと特殊だったっちゃ特殊だったんだけど。……俺はもう中2の時点で、絶対デビューしてこうなるなっていうのがすごいわかってたから。だから中3の時点ですごい矛盾と格闘したんだよ。なんで俺受験勉強してんだって。だって高校行く必要ないんだもん。ほんとに意味ねえことだと思ったの。で、お父さんに相談したら……『俺なるから』って言ったら、だったら条件があるって言われて。『18までに調理師免許と大検を取ったら好きにしていい』って言われた。これは俺には、藤原と違ってさ、要は完全な目標。これさえやれば、もう好きなように出来るっていう」 |
| 藤原 | 「チャマ、店継げとも言われてたしね」 |
| 直井 | 「うん。てかそれはウチのおじいちゃんの希望で、赤ちゃんの頃から聞かされてて。俺はそれを裏切るっていう—-」 |
| 藤原 | 「だからチャマがバンドをやるっていうのは、それをした上での、覚悟だったんだよね」 |
| 直井 | 「そう。だから俺は、自分のプロになるって言う気持ちと、家族の希望の間ですごい格闘してたの。そん中で藤くんが、ある日、”ガラスのブルース”を書いてきたんだよ」 |
高校時代~ガラスのブルース~
| 藤原 | 「“ガラスのブルース”は、学校辞めてゆっくり、ちょっとずつ書いていった曲で」 |
| 直井 | 「その頃、みんなそれぞれのことやってたんだよね。ヒデちゃんとヒロは高校生で、俺は調理師免許と大検の勉強という、そういう感じの期間で。いろんな気持ちがあってすげー複雑だった。……でも前向きだったかな」 |
| 藤原 | 「覚えてんのは、とにかく3人がウチに来てくれたじゃん。でまあ、ゲームやったり話したり。 俺寝てたりとか(笑)そういう感じで。俺の生活は……バイト探しに行って、 実際やってみてソリが合わなくて辞めたり。1日とか、長くて1週間とかね(笑)。4個ぐらいやった。やっぱみんな、俺がバイト決まったって言うとすごい喜んで、辞めちったってなるとすごい心配そうな感じで(笑)。でもなんか、ほっといてくれよ感も俺の中にはあって。ダメな感じのほっといてくれよ感。 そいで…………初めてそこで、自分の存在とか結構軽いなぁみたいな(笑)、『ああ存在の希薄さよ』みたいな、そんなことを思った。 なんか薄っぺらいって感じがした。サイズの問題じゃないの。厚さの問題。ほんと薄かった。景色が透けるぐらいのペランペランさ。 そんなような存在だな、と。いてもいなくてもみたいな、そこまで考えて。 それに感慨があったわけじゃなくね。『俺っていてもいなくても取るに足らない存在なんだな、はあ』ってそういうんじゃなくて、ただその事実を知ったの。 ビックリしちゃった。で、その間にやってた作業ってのが、ほんと1日1行ずつぐらいの感じで、”ガラスのブルース”の詞を書いたり、コードを繋げたり、メロを繋げたり。 すげーゆっくり書いてたの。……そ れは明日に向けてとかいう意識は全然なくて。この作業が終われば何かがあるかもなって漠然としたもんはあったかもしんないけど、俺は音楽で食ってくことになるとかっていう気持ちがあってとかじゃなくて、それよりももっとプリミティ ヴな感じだった。なんか表現してみたくなったんじゃないかな。……『楽しいぜ』とかそういうんじゃなくて、もうなんか『俺です』みたいな、IDカードを作りたくなったんじゃないかな、おそらく。学校で『IDの作り方』みたいな説明書が配 られて、それになぞってIDカードを作って、それを我がもの顔で提示してる学生って多いと思うの。で、俺も漏れなくそれだった感じがするんだ。でもなんか……あれは誰かが用意してくれた鏡に自分を映して、『これが僕です』つって人に見せてただけなんだなっていう、ね。すごい外的なもので。で、もっと内側に入った時っていうのはどこにも鏡がないじゃん。だから、鏡を作ってたんだろうな、きっとな」 |
| 増川 | 「なんか……よく藤原の家に行ってたのは、ちょっと心配って気持ちがあったから。なんか……ずっと家にいたからさ」 |
| 藤原 | 「それを俺は全然素直に受け入れられなかった。友達って感じは嬉しかったんだけど。だからつかず離れずみたいな感じ、3人に対する姿勢としては。それ以上は踏み込んで欲しくはないんだけど、でも離れて欲しくもねえみたいな感じで。すっごい厄介だったな(笑)。それでも火曜日の練習だけはしてたんだよね」 |
| 升 | 「まあ、練習ではないけどね(笑)、会ってたよね。集まって、練習したり何かしたり。その集まることが第一って感じ。別に藤原のリハビリとかって意識はないんだけど」 |
| 増川 | 「そういう意識はないね」 |
| 藤原 | 「俺もう、リハビリとかしようと思ってなかったし。逃げてたよね、完全に。逃げ込んでるだけ。リハビリってだってこう、立ち向かう感じじゃん。そういう言葉は絶対似合わないと思う。でも、腐ってたかっていうと……まあ腐ってたんだけど、”ガラスのブルース”は書いてたんだよね、ちょっとずつちょっとずつ。でも自覚的なものはひとつもなかった。……やることなかったんだろうね。やることなかった。空っぽになった、ほんとに(笑)。……あの虚無感はものすごいものだった。……”ガラスのブルース”はさ、1回拒否した世界に対する俺のアンサーだったんだと思う。…………愛しい気持ちだよ、きっと。自分ていうほんとに矮小な存在に対する気持ちだったり、あと……すごく斜めに見ることを覚えてしまったから、そっから真っ直ぐ見直すことが出来なくなってしまったから。結構今でもそうだったりするんだけど。目に映るものっつーか感じることっつーか、そういうのを斜めなまま愛しく思える気持ちはあったんだけど、それを否定してたと思う、当時の俺は。でもやっぱ、それこそが俺自身を否定することであって。そういう意味で、”ガラスのブルース”が完成することで俺は救われたんだと思う。あの曲が出来た時…生きて行こうって思った。ふふっ。ベクトルや形がいかなるものであっても、時計が動いて呼吸が続く限りは生きて行こうって思ったんだよね。…………で、それを3人に持ってった。『曲が出来たー!』みたいな感じじゃなく、『1曲出来たよ』みたいな感じで持ってったの(笑)」 |
高校時代~伝わること~
| 直井 | 「すっごいさりげない感じだったよね。でも初めて……日本語で」 |
| 藤原 | 「うん。日本語で作ったってとこには、大きな意味があったと思う。絶対あったと思う。なんで日本語で書こうと思ったかはよくわかんない……たぶん某音楽レーベルのひとに言われたこともきっかけになっただろうし。……キーワードがいくつもあるじゃん、あの曲には。そのキーワードっていうのが、既に息づいていたから。『詞を書きたいんだ』って意識があったんだと思う。英語でやってた時なんて、ほんとにノリだったから。なんとなーくのストーリー、大まかなテーマみたいなのはあったりしたけど。でも大したことないもんで。『俺は怒ってる』的な感じとか『俺は楽しい』的な感じとか、その程度のもんで。まあ今思うとそれはそれでいいなと思うけど(笑)。なんつーんだろ…………曲が出来て、3人に聴いてもらったら反応が違ったんだよね。『いい曲だね』っていう言葉が……『いいねこの曲、楽しいじゃん、カッコいいじゃん』っていうのではなくて、単純に『いい曲だね』っていう感想があって。『いい曲だね』って言った後に、ちょっと沈黙を挟んで『ああ、いい曲だ』って言うような感じ(笑)。そういう扉を開けることが出来たのかもしれない。きっとそういう曲だったんだと思う。……いつもたまってる喫茶店があったんだ。その喫茶店でも何行か”ガラスのブルース”の詞を書いたりしたんだけど。……そう、4人でデモテープを作ったの、4トラックのMTRで。最悪な音だったんだけど(笑)、いつも俺、それウォークマンに入れて聴いてて。で、ひとりでその喫茶店にいて、なんかボケッと本とか読んでたら、学校終わったちょっと悪い奴らがその喫茶店に来て。それで『何聴いてんの』って話になって、『いや、こないだ曲が出来て、それ聴いてんだよ』って言ったら『ちょっと聴かせてよ』みたいになって。正直ちょっとね、恥ずかしいなってのがあったの。その当時はメロコアが全盛期で、みんなオフスプリングとか聴いててさ。スケーターって文化が来日した頃で、腰履ばきしてるような奴らばっかで。みんな全然いい奴らだったんだけど。だから、要は……”ガラスのブルース”って結構ポップな部類に入ると思うんだ、ジャンル分けをしたら。だから受け入れてもらえんのかなっていう。でも『聴かせてよ』って言われて『別にいいよ聴かなくて』って言うのもなんだしなみたいな(笑)。でも結構俺ん中で、そこで聴かせることが出来たってことはすごい重要だった。聴いてもらって、『すごくいい』って言ってくれたの。『こんなこと考えてんだね、すごい鳥肌立った』的なことを言ってもらえて。『学校辞めた後はどうなることかと思ってたけど、こういうことやってたんだね、安心した』みたいなこと言われたりして。あれはすごいデカかったと思う。メンバーがいいって言ってくれたのは、象徴的に今のバンプ・オブ・チキンに繋がってると思うんだけど、そのバンプ・オブ・チキンが、今メジャーに上がってるひとつの理由として—-ただの音楽好きがメジャーに上がってるひとつの理由として、あの瞬間があったと思う。すごい快感だった。伝わることって快感なんだなって。『ああ、俺こういう気持ちあったんだけど上手く言葉に出来なかったんだけど、そうだよこういうふうなことなんだよ』みたいなことを言ってる不良がいたりして。すげー嬉しかった。だから歌が伝わったっていうさ。……”ガラスのブルース”が出来た時に、アレンジや文化を超えて、単純に『歌』だと思ったの。ほんと、アレンジや文化や時代じゃなくって歌が伝わったっていうのがすっごい嬉しくって」 |
| 増川 | 「俺は、最初聴いた時は、ほんとに単純に『わかった』っていう感じ」 |
| 藤原 | 「そうだ、初めて聴かせたのが増川だったんだ。ギターで弾いて聴かせたんだっけ?」 |
| 増川 | 「そう。なんか紙に書いてあったのを見ながら俺は聴いた、たしか。わかるじゃん、日本語だから。それがすごいことだなって。すごいなっていうか……それは初めてだったし」 |
| 藤原 | 「ビックリしたよね」 |
| 増川 | 「ビックリしたね」 |
| 藤原 | 「わかるって言われたことも、俺はわかってもらえたってことも、ビックリしたな。なんか新世界だった」 |
| 増川 | 「もちろん、すごくいいなと思って、『すごくいい』って言って(笑)」 |
| 藤原 | 「ふふふ」 |
| 升 | 「なんか周りの反応ってのが全然違った。俺らは別に新しい曲のひとつって感じでやってんだけど、ほんとに周りのひとが、『今やったのもう一回聴かせてよ』みたいになって。だから、聴いてるひとにも伝わってるっていうのがすごいことだなって思った」 |
| 藤原 | 「ある種の違和感すらあったな」 |
バンプ・オブ・チキン~ガラスのブルース優勝~
| 直井 | 「なんかね、俺、好きな女の子がいたんだよね、そん時」 |
| 藤原 | 「いたねえ」 |
| 直井 | 「うん。その子が、『何、今の?』って言ったのに驚いた。今までほんとに、『何やってんのかなこのひと達?』っていう(笑)」 |
| 藤原 | 「そういう目で見てるひと多かった(笑)」 |
| 直井 | 「だからヴォーカルの声がもっと聴きたいとか(笑)、そういう反応だったんだけど。…………『なんかわかんないけど、4人でそうやって音楽やってんのってすごいね』っていう反応が一気に出てきたよね」 |
| 藤原 | 「で、さっそく、命試ししたんだよ。その夏に”ガラスのブルース”で某大会に出たの。で、優勝しちゃったんだ(笑)。ビックリした。その大会はとってもハイ・レヴェルで、クオリティの高いバンドが多かったと思う。大会の名目が『新感覚オーディション』っていう、要はメジャー・デビュー・オーディションって触れ込みだったんだよね。全国大会まで行けば業界人がわっさ来るぞっていう。だから本気の奴がいっぱいいて。でも俺らは『デビューするぞ!』なんて言葉は会話の中に出てこなかった、全然。まあ漠然と、これに勝てば生活してける的なものもあったかもしれないけど、でもとにかく命試し、自分試しみたいな感じで。そういう気持ちでやって1個勝ち上がって、1個勝ち上がったら次もう本選で。天王洲アイルだっけ?デカいとこでやったの。その時……みんなCD聴いてるみたいに上手いって思った(笑)。みんなお洒落で、みんな上手くて」 |
| 直井 | 「ステージ用に衣装変えててビックリしたよ。あと、髪の毛にジェルつけたりしてるの」 |
| 藤原 | 「俺らほんと、着の身着のままで。エフェクターも持ってなかったよね(笑)。やっぱ“ガラスのブルース”はあのアレンジでいくと若干のギターの歪みとか欲しいじゃん。でもないから、クリーントーンのままやるっていう。ちょっとニュー・ウエイヴな感じ(笑)」 |
| 直井 | 「意図せずね。わかんなかったもん」 |
| 藤原 | 「だからすごい上手いひと達がいっぱいいて、こういうひと達が勝ち上がっていくんだろうなーって思ってた。だから結果発表になって全員ステージの上に立たされた時とか、もう俺ら、どうでもいい感じだったよね(笑)」 |
| 直井 | 「期待すらしてなかったよね。遊んでた」 |
| 藤原 | 「なんか面白れー動きをしたりして(笑)」 |
| 升 | 「すげーバカやってたよね(笑)」 |
| 藤原 | 「でも正直、高校生部門のグランプリぐらい獲れたら嬉しい的なものもあったんだけど、それはパンクをやってるバンドが獲って」 |
| 増川 | 「どんどん決まってったんだよね、いろんな賞がさ。で、あと1個になって」 |
| 藤原 | 「絶対優勝だと思ってたバンドがあって、あのひと達が優勝だろうなって思ってたら、『バンプ・オブ・チキン!』て呼ばれて。俺が覚えてんのは、自分が呼ばれたっていう実感がなくて、チャマが俺の背中を押した(笑)。『俺らだよ!』って、後ろから」 |
| 直井 | 「すげー飛び跳ねたな」 |
| 増川 | 「飛び跳ねて審査員のとこまで行って、ずっと喜んでた」 |
| 藤原 | 「でもさ、グランプリ獲っても何も変わんなかったよね。俺トロフィー楽屋に忘れそうになったんだよ(笑)。そんぐらい意味のないものだった。そんで地元に帰ったら駅前とかに悪ぶった友達とかがいて、『お前ら今日大会だったんだろー、どうだった?』『優勝したよ』とか言って、2~3日ワッとなって……」 |
バンプ・オブ・チキン~制作会社の出会いその1~
| 直井 | 「あとは普通の生活だよね」 |
| 藤原 | 「そうそう。レコードレーベルとかから電話がかかってくるでもなく、ただ日々淡々と過ぎてって。で、まあそこら辺から自分らでブッキングしてライヴやることを覚えた。千葉で」 |
| 直井 | 「千葉ルックとかルート14」 |
| 藤原 | 「あと千葉アンガって小屋とか、本八幡のサードステージとかでもやらしてもらったり。そういうの繰り返してたら、その優勝した大会を観てくれてた、今も一緒に仕事してる女のひとが『下手だったけどいい歌だった』ってだけで東京からわざわざ観に来てくれて。そん時は英語のオリジナル曲と何曲かの日本語の曲をやってたんだけど。……”くだらない唄”があったかな。”アルエ”はギリギリなかったかも」 |
| 直井 | 「“18years story”っていう英語の曲やってたよね」 |
| 藤原 | 「あと、“ワースト・ライフ”(笑)」 |
| 直井 | 「“トランス・ライフ”ってのもあった(笑)」 |
| 藤原 | 「“モーニング・グロウ”ってのもあったし”サンシャイン”ってのもあった」 |
| 直井 | 「ほんと英語ばっか(笑)」 |
| 藤原 | 「でも”ガラスのブルース”以降は本当に『歌』を作ってて。英詞でも『詞を書いてる』って感覚があった。今よく俺はさ、『曲は俺の子供みてえなもんだ』みたいなことを言うじゃん、昔の曲も今の曲も大差なく愛せるって。そういう意識はもうその頃からあった。そいで、その彼女の感想は、下手くそだけど曲がいいって。あと、4人の姿勢がいいって言ってくれて。とにかく興味を持ってくれて、名刺をくれたんだ。その名刺を増川が食ったの(笑)」 |
| 増川 | 「(笑)すげー失礼な話だよな」 |
| 直井 | 「(高い声で)食べられんじゃねーの?』って言って(笑)」 |
| 藤原 | 「でも俺らも、その食ってる姿を見て『やられた』『先を越された』みてーな(笑)」 |
| 直井 | 「だからズボンを下ろしてみたりして」 |
| 藤原 | 「そうそう、ケツに挟んでみたり。それで『なんなんだこいつらは』とは思ったらしいんだけど(笑)。でも、練習見たいってチャマん家まで来てくれたり、何曲かデモテープあるの?つって。その頃はもう一応曲が出来たらMTRで録るようにしてたからさ。で、そのテープを事務所の社長さんに聴かせてくれて。それで、事務所の社長さんも俺らに興味を持ってくれて、代官山にお呼ばれされて」 |
| 升 | 「大東京ですよ(笑)」 |
| 直井 | 「もう自慢しまくったもん。千葉から東京に行くっていうのは、俺らにとっては大旅行」 |
| 藤原 | 「イヴェント。遠足。修学旅行」 |
| 直井 | 「4人で写真とか撮りながら行って。で、その社長さんは『可愛いね、可愛いね』ってずっと言ってた。音楽がどうとかじゃなくって、4人の存在のすごさを—-」 |
| 藤原 | 「『すっごくいいんだよね、この4人の空気の感じがね。喋ってみても、すごく音楽に対する姿勢もちゃんと持ってるし』って」 |
| 直井 | 「そっから転がりはじめたよね。そのふたりに出会ったのが……」 |
| 増川 | 「デカかった」 |
| 藤原 | 「そのひと達は制作会社としてじゃなくて、単純にひととしての付き合いをずっとしてくれて。だからすぐに契約書出すなんてことは全然なくて。『一緒にやってこう』って告白されたのは、それから2~3年後の話だから」 |
| 直井 | 「すっごいステキなひとだよ。別に俺らに金を出すとかいう感じでもなくて。『ただ見ていたい』っていう」 |
| 藤原 | 「『守りたい』って言われたの。全然ピンと来なかった。『いろんな誘惑があるからそれから守りたい』とか言われてて—-今だったらよくわかるけど。実際守られてたし」 |
| 直井 | 「で、その女のひとから『オールナイトのイヴェントをやるから出ない?』って言われて出たのが、初の東京ライヴ」 |
| 藤原 | 「(下北沢)クラブ251」 |
| 直井 | 「俺らの出番は深夜の2時からとかで、俺らすっげー眠くなっちゃって」 |
| 升 | 「だから帰りもなかなか臼井に帰りつけなかったんだよね。どんどん寝過ごして(笑)」 |
| 藤原 | 「寝過ごすから引き返すんだけど、また寝過ごして、みたいな(笑)」 |
| 直井 | 「でもね、今考えてもほんとにステキな時間だった。まず初めて4人で東京で、『クラブ』って名前のつくところに出て」 |
| 升 | 「初めてブラックライト見て、ずっと歯ぁ出してたよな(笑)」 |
| 3人 | 「あはははははは!」 |
| 藤原 | 「『おめーの歯ぁ変だよ』とか言って(笑)」 |
| 直井 | 「帰る時、俺ら始発に乗ったんだよね、上野から。で、誰もいなかったから、ひとり席1個ずつ使って寝そべって寝て。でも起きたら満員なの(笑)。あの朝の光が忘れられない」 |
バンプ・オブ・チキン~制作会社の出会いその2~
| 藤原 | 「実は、あの大会をきっかけにして声かけてくれたのは、その制作会社の他にもうひとりいたんだよね。個人でマネージメント的なことやってるひと。そのひとが電話をしてきて、大会で観てすごい興味を持ったから他の曲も聴いてみたい、ライヴがあったら観たいって言ってくれて。しばらくは電話のやり取りで、テープ送ったりしてて、で、会いたいって言われて会ったの。そのときにもうひとり連れてきたんだけど、そのひとは破天荒な感じだったよね(笑)」 |
| 直井 | 「『お前らイギリス行けよ』とか、そういうひとだったよね」 |
| 藤原 | 「勉強しろって言ってCDもらったよね。『あ、これが業界人なのかな』ってふたり組だった、善くも悪くも。で、そのひと達が早速、某大手レーベルのひとを紹介してくれて。その人も俺らに興味持ってくれて。……なんかね、ちょっと怖かった、ある意味。何でも買う買うって言うの。『CDいっぱい買ってくれ、ウチの会社の名前で領収書切っといてくれ』って」 |
| 直井 | 「嬉しかったよね」 |
| 藤原 | 「でも怖かったでしょ、ちょっと。だから、全部CDとか買ってやるからいっぱい聴いて勉強しろっていう。あと、『お前らの楽器の音良くねえから楽器買おう』とか言われたりして」 |
| 直井 | 「買ってもらったよね」 |
| 藤原 | 「ていうか買わせた、って感じだった。『利用してやろう』ってところに落ち着いたんだよ(笑)。だからもう、悪なら悪でいいし、立ち回りは悪でもそれは音楽に対する純粋な気持ちだから、俺らの中では善だったから。もう全然、頭ひとつ下げずに上手に利用させてもらって。申し訳ない話だけどね」 |
| 直井 | 「でもやっぱ実際愛されてたよね」 |
| 升 | 「うん、そういうのはすごい伝わってきた。楽器買う時にしても『後で返せ』とか絶対言わないし。『ほんとにそれは君達の財産になると思ってやるから』みたいなことを言われて」 |
| 藤原 | 「でもね、ある時、その会社のショーケース・ライヴに出されそうになったんだよね。 ショーケース・ライヴって説明がないまま、『デカい会場でライヴやるからお前らも出ろよ』って言われて。やってみたいじゃん、デカいとこで。で、やろうかなって返事をして。 で、さっき話した制作会社のひとにね、こういうライヴをやることになったんだって言ったの。そうしたら、『ちょっと待って、それショーケース・ライヴだよ』って、その実情を説明してくれて。要はだから、そのレーベルの財産という形でライヴに出されるわけじゃん。叩き売りに出されるわけじゃん。だから『そんなもんだったんだ、それは絶対ダメだ』って断ったの。そしたら『どうして僕らを信用して出てくれないんだ』っていうことになって、『いや信用するしない以前に、このライヴの精神を説明しなかったことは おかしいだろう』と。『僕らは確かにあなた方に恩も感じているけれども、義理で出ていいライヴじゃないと思うし、義理で所有物になっていいもんじゃねえし』って。丁重にお断りした。 で、それが縁の切れ目になったんだよね。『これをひとつの返答として受け取るから、これからは今までのようには応援できなくなる』って言われて。でもそれは当然のことだと思ったし。そこで俺ら『いやそれは違うでしょ』とか言い出したら、それこそ違う話だから。 それこそ甘えてるだけだから。……でも『これからも応援し続けるからね』って言ってくれて、それがすごい嬉しかった。 自分らの、そのひと達に対する意識ってのを恥じた。利用してやれ的な部分もあったからさ。 ……で、そういうことがありながらも、ファースト・ツアーやったりして。でも同じ年、’97年の秋ぐらいに、一旦バンドを休止することになるんだよね」 |
リンク
リンク
BUMP OF CHIKENヒストリーブック
2004年発売「アルエ」の応募企画に当選した限定3000冊のヒストリーブックの内容。
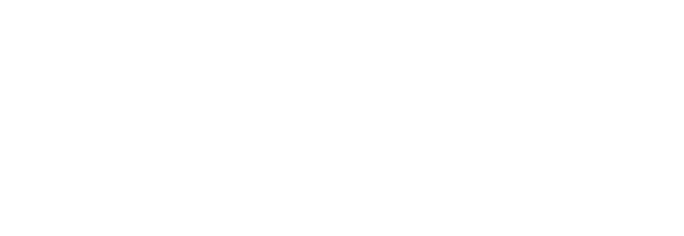





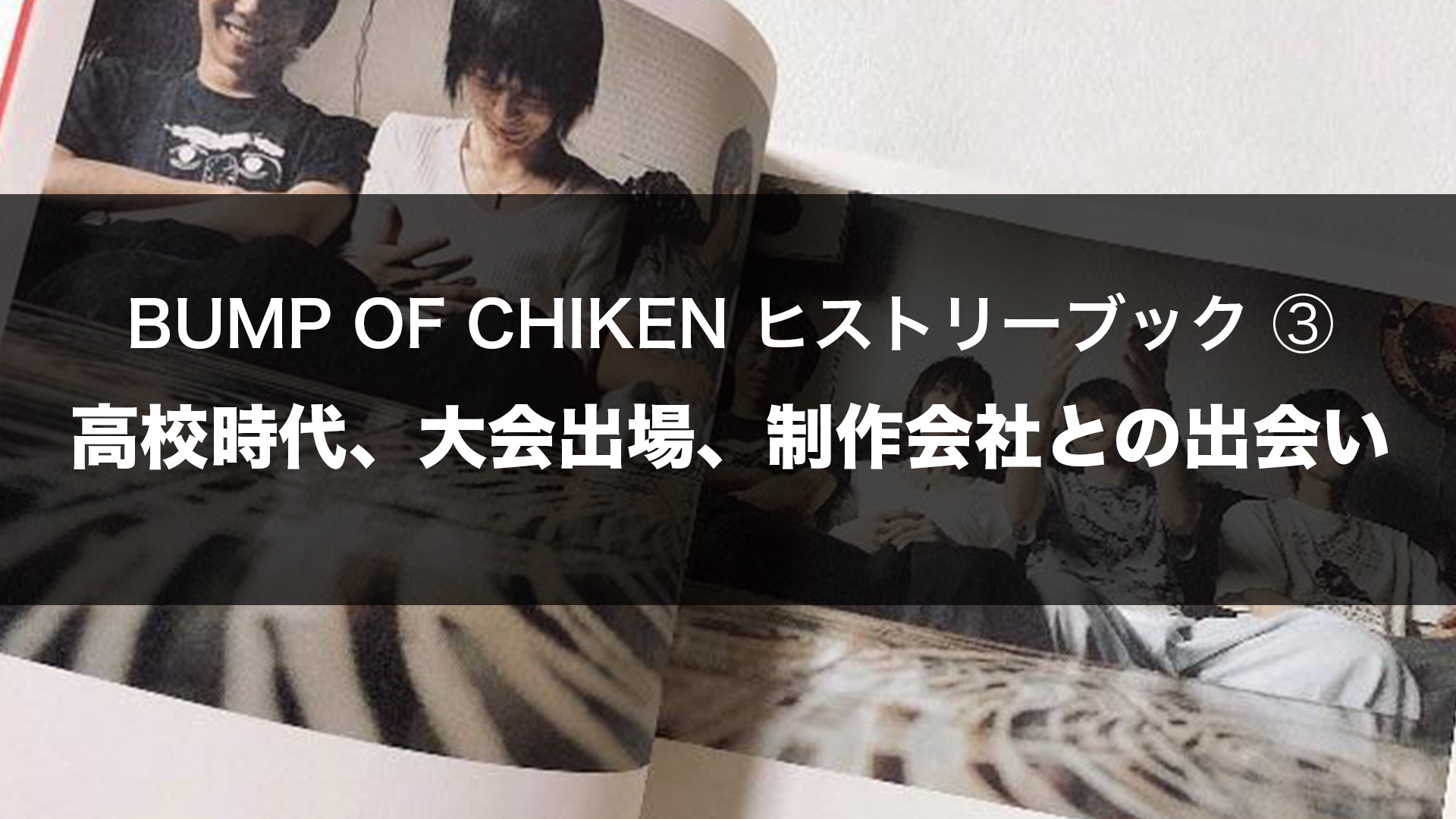




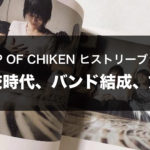



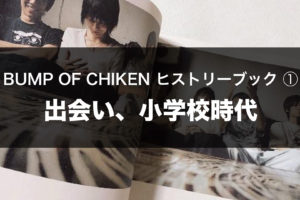


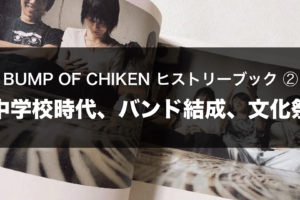











コメントを残す